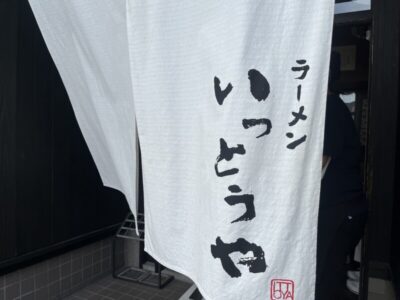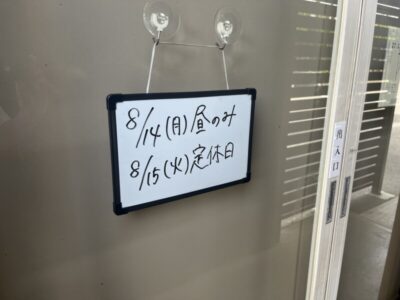平標山へ2023年9月12日(火)
9/10
嫁さんと山フレンド夫婦と私、4人で平標山に登ってきました。
坂戸山から始まって、徐々にグレードを上げてようやく中級レベルの山へ
この山を登れれば3,000m級の北アルプスに連れていけるはず。
早朝5時に自宅出発
前日にゴルフしていたので足が重いし、疲れがたまっていてか眠い。
不安な気持ちを胸に登山口駐車場へ到着。
18時半、思ったほど駐車場は空きスペースが多く空いていた。
最近の猛暑で登山を控えているのだろうか?

支度を済まし、いざ出発
今回は登山靴をゴローからトレイルラン用の靴に履き替えて登ってみることに
先日の沢登りの下山で使用してみるとグリップ力が高く、クッションも優れていて歩きやすかったので
今回は登りも下りも使ってみてどんなものか試してみたかった。

気温は高くないものの湿度は高く、そして風も吹かないうっそうした急登を上がる
いきなり3合目までがキツイのがこの山の特徴だ。
鉄塔さえ超えれば景色は開けるのでそれまでは我慢

鉄塔を越えて松手山まで
ここまでくればそよ風が疲労を吹き飛ばしてくれる
緩やかな稜線をお散歩
気持ちいばかり

松手山で一息
嫁さんからパイナップルビスケット?という謎のお菓子をもらうも
口の中の水分を全部もっていかれて窒息しそうにWW
登山でビスケットは危険だ。

松手山から再び現れる急登を

ここさえ登ればあとは楽園

ついに到着しました。
山頂は残念ながらガスで展望はなく
昼食をとりながら視界が広がるのを待つと
奇跡的に仙ノ倉へと続く緩やかな稜線が現れた
ここぞとばかりに写真に収める
 時間があれば歩きたかったけど
時間があれば歩きたかったけど
余裕もないのでここでおります。
今回は山の家の周回は膝が痛くなるので、ピストン下山

それにしてもトレランシューズは最強だ。
下り道は恐る恐る降りていたのが、ピョンピョンと跳ねて降りれるじゃありませんか!
そしてクッションも柔らかいせいか、膝も足も全く痛くない。
防水性はイマイチだろうから雨の日以外はこいつがレギュラーになりそう。
登山靴は進化している。というか俺が古すぎたのかも。

そして無事下山
嫁は不思議とこのポーズばかり(笑)
今回も水分を1ℓしか持っていかなかったので喉がカラカラ(反省)
自販機でコーラ500ml一気飲みして、蘇る
コーラはやっぱり最高だ。
ついに平標制覇できたので、次の目標はいよいよ本格的な山へと行ける
白馬岳か燕岳か、またひとつランクが上に行けるのが楽しみに